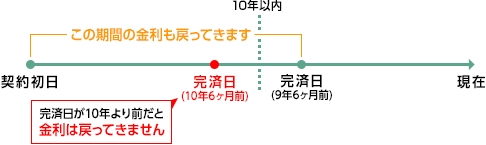過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
過払い金の時効は10年|最終返済日が起算点
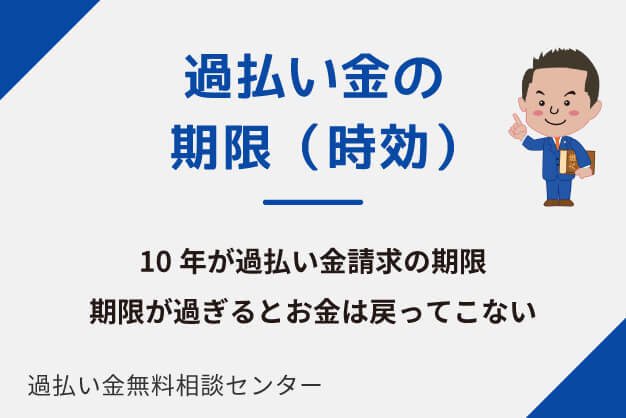
「過払い金が請求できる期限とは?」
「過払い金の時効は10年なの?」
過払い金には請求できる期限があり、これは時効の考えが元になっています。起算点は「最後に利用した日」で、ここから10年で時効になります。
例えば、2020年6月30日完済なら2030年6月30日が、過払い金の請求期限です。
なお、複数回の完済がある場合には注意。その途中完済の完済状況によって、過払い金が大きく減ってしまう場合もあるからです。
2013年完済の方は、2023年で期限を迎えるので注意しましょう。
過払い金とは、過去に利息で払いすぎてしまったお金のことです。
2007年頃までは、20%を超える違法金利も多い時代でした。この違法金利で返済したお金が、払いすぎたお金(過払い金)として戻ってくるわけです。
なお、2008年以降は、法定金利のケースが多く過払い金発生の可能性は低いと言えます。
過払い金の対象はキャッシング
過払い金は、消費者金融・クレジットカードでお金を借りた場合が対象です。
銀行のカードローンは対象外です。また、クレジットカードで買い物でカードを利用しただけでは、対象になりません。そして、車や住宅ローンからも過払い金は発生しません。
過払い金の期限(時効)を考える上では、「起算点」がポイントです。
起算点とはスタート日であり、この日から期限(時効)が進行します。
過払い金が請求できる期限(時効)は、原則として最終利用日から10年です。
※2020年4月1日以降に完済の場合
「過払い金があることを知った時」から5年。もしくは、完済から10年。
2020年3月31日までに完済した場合
この場合は「完済したとき」が起算点、その時から10年で過払い金は時効です。
例えば、2015年7月1日完済では、7月2日0:00が時効の起算点。そこから、2025年7月1日24:00をもって時効となります。
2020年4月1日以降に完済した場合
「過払い金があることを知った時」から5年か、「完済した時」から10年で時効です。
例えば、2021年3月24日に完済し、過払い金があることを5月24日に知ったとします。
その場合には、知った5年後の2026年5月24日が請求期限です。知らなかった場合でも、完済から10年後の2031年3月24日には、時効を迎えます。
途中完済と時効の関係
①一度も完済したことがない(一連)
②途中で完済。再利用している(分断)
過払い金の時効において、この「一連」か「分断」は非常に重要なポイントです。
①②いずれの場合でも、過払い金は請求できます。ただし、②のように途中完済があると、時効によって過払い金が少くなるケースがあります。
分断になるとどうなる?
例えば、2000年からプロミスを利用し2014年に完済。その後、2017年に再利用を行った場合でみてみましょう。
この場合、2014年までの過払い金は、2024年で時効となる可能性があるのです。
途中完済があったからといって、100%分断になってしまうわけでもありません。分断か?そうでないか?は、取引に一連性があるか?ないか?などの事情で判断されます。
分断になる例
(分断になる可能性がある場合)
・途中完済~再利用が1年を超える
・途中完済時に解約を行っている
・再利用時に、契約(会員)番号が変わった
・再利用時に新たなカードを発行された
・再利用時に再び本人確認や与信審査を受けた
例えば、途中完済後に解約。その後、3年以上経って再利用。新たなカードが発行されたケースでは、分断になるでしょう。
分断にならない例
反対に、完済後、半年ぐらいで再利用。カードは以前のものが使えて、限度額も以前の200万円のままであった。このような場合は、分断にはならないでしょう。
(分断にならず一連の可能性が高い場合)
・途中完済時に解約をしていない。
・途中完済~再利用までが1年以内。
・再利用時に以前のカードが使えた。
・再利用後も、以前の契約(会員)番号であった。
・1998年~2002年で一度完済。
・2003年再利用~2018年に完済。
2002年に一度完済し解約。2003年から新たに利用している場合です。
この場合2002年までの過払い金は10年後の2012年に時効。取戻せるのは、2003年以降の過払い金となります。
分断で過払い金が0円になってしまう場合
・2002年~2011年で一度完済し解約。
・2014年再利用~現在も返済中。
2002年~2011年までの契約がいったん終了。分断が認められると、ここまでの過払い金は時効です。また、2008年以降は適正な金利になっているため、再利用分から過払い金が発生しません。
結果的に、1円も過払い金が戻ってこないケースです。
「もう支払わなくてよいと言われ、返済をしなくなった」
「返済ができなくなったけど、何も言われなかった…」
こうしたケースも、過払い金請求の現場ではたまに見るパターンです。
例えば、2006年を最後に返済ができなくなり、その後支払っていないという場合。
滞納している場合の、過払い金の時効の起算点は「最後に返済をした日」です。この日から10年で時効になります。
過払い金で滞納を解消できる場合
なお、滞納しているのに何も連絡がないというケースもあります。
この場合、「実は多額の過払い金が発生しているから」という理由の場合もあります。
例えば、表面上は50万円の支払い残を滞納しているが、実際には150万円近い過払い金が発生している場合がこれにあたります。
この場合、無理に督促をして、過払い金請求をされたほうが、カード会社は困るなので、未払いでも何も連絡がなかったというわけです。
10年ギリギリの過払い金請求
「完済から10年ギリギリ…今から依頼しても手続き中に10年経ってしまうのでは…?」というケースです。
結論から言って、過払い金請求を依頼される日が10年以内であれば問題はありません。
手続き中に10年を超えそうな場合には、対策があります。
6か月の期限の猶予を持てる
過払い金請求をスタートするときは、介入通知という書面をカード会社に送ります。
この書面に、〝過払い金が発生していればこれを請求します。本書面は民法150条の催告とします〟という内容を盛り込みます。
この催告により、6か月間は時効の完成猶予を持つことができます。
裁判所に訴えると時効期限がリセット!
催告を行っただけでは、あくまで6ヶ月の完成猶予しかありません。
そのため、完全に時効を更新(中断)させるには、裁判所に訴えを起こす必要があります。裁判所に訴えを起こすと時効期間は更新されます。
10年が過ぎても過払い金が請求できた事例
完済から9年11か月で過払い金請求をスタートしたRさんの事例。
まず、介入通知を送付。時効の完成猶予(6か月)の間に、取引履歴の取寄せや過払い金の計算を行い、裁判所に訴えを提起しました。
過払い金の訴えを提起した段階では、完済から10年3ヶ月が経過。しかし、6か月の完成猶予期間があったためセーフというわけです。
当ホームページについて

当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
クリックすると移動します
本サイトの執筆者

司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士18年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ
過払い金のお問合せはこちら

運営事務所概要

- 司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
- 横浜市西区高島2‐14‐12
ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分) - TEL:045-328-1280